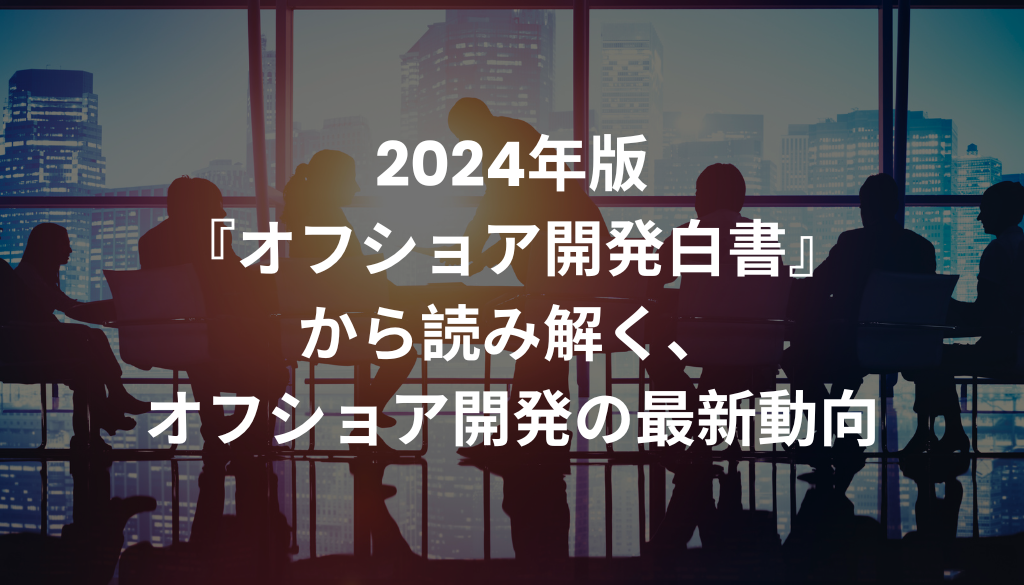近年、柔軟かつ継続的な開発体制を求める企業の間で「ラボ型開発」への注目が高まっています。
従来の請負型開発とは異なり、外部の専属チームと長期的に協働するこの開発手法は、開発のスピードや柔軟性の向上、ノウハウの蓄積、コスト最適化といった多くのメリットをもたらします。
本記事では、ベトナムで長年にわたりラボ型開発ソリューションを提供するSHIFT ASIAの知見をもとに、ラボ型開発の特徴やメリット・デメリット、請負型開発との違い、適した案件の特徴、費用感、そして成功のためのポイントまでを分かりやすく徹底解説します。
ラボ型開発とは
ラボ型開発(ラボ契約・ODC)は、外部の開発会社側に一定の期間において自社専属の開発チームを確保し、継続的に開発や運用を進める契約形態であり、開発手法です。
ラボ型開発の契約形態は基本的には準委任契約であり、請負型開発(請負契約)のように「事前の取り決めに基づいて完成した成果物を納品してもらう」という契約ではなく、「依頼者側の専属の開発チームを一定期間確保する」という契約になります。そのため、ラボ型開発では依頼者側の特有の開発スタイルや、開発対象となるプロダクトの知識や文脈がチームに蓄積されるというメリットがあります。
ラボ型開発は日本国内のニアショア開発で用いられることもありますが、ベトナムをはじめとする海外の開発会社を活用したオフショア開発で特に広く活用されており、「ラボ契約」「オフショア開発センター(Offshore Development Center、ODC)」などと呼ばれることもあります。
あらためて、オフショア開発とは|オフショア活用が進む理由とメリット・デメリット
ラボ型開発の規模や契約期間は、数名規模で半年〜1年程度から始めることが一般的ですが、SHIFT ASIAのように「最小1名で1ヵ月から開始できる」など、小規模・短期間でのラボ契約が可能な開発会社も増えてきています。
ラボ型開発においては、依頼者側と開発会社側のPMやブリッジSE(BrSE)と直接やり取りしながらタスクを配分・調整していくという運用が一般的です。そのため、ラボ型開発ではプロジェクトの途中で仕様や優先度が変わっても柔軟に対応しやすいという特徴があります。
SHIFT ASIAでは、株式会社SHIFT(プライム市場上場)で培われた開発やテストのナレッジ、ベトナムのハイスキルエンジニア、豊富な経験をもつ日本人PMとを組み合わせ、日本と同等以上の価値をリーズナブルな価格で実現。品質・スピード・柔軟性に優れたラボ型開発を提供しています。
SHIFT ASIAのラボ型開発は、「最小1名・1ヵ月から」お試しいただけます。お気軽にご相談ください。
>>ソフトウェア開発ソリューションのページへ
>>ソフトウェア開発ソリューション紹介資料のダウンロードページへ
>>オフショア開発会社選定ガイドのダウンロードページへ
>>導入事例ページへ
>>お問い合わせページへ
ラボ型開発に注目が高まる理由
近年、ラボ型開発に対する注目が高まる背景には、日本のビジネス環境におけるいくつかの構造的な変化があります。
まず、日本国内では深刻なIT人材不足が続いており、スポット的な請負型開発やSESでは、継続性や柔軟性が求められる開発現場に対応しきれないケースが増えています。
また、ユーザーニーズの多様化や加速する市場の変化スピードに対応する形でアジャイル開発がますます一般化しており、開発途中での仕様や優先度の変更に柔軟に対応することを前提とした開発が主流になりつつあります。このような環境では、開発会社に成果物を一括で発注する従来の請負型開発よりも、自社専属の開発チームと継続的に協働できるラボ型開発のほうが適しています。
あらためて、アジャイル開発とは|その概要から進め方、メリット・デメリット、開発手法について
さらに、リモートワークやクラウドツールの普及により、オフショアを含む遠隔チームとの協業による開発も現実的な選択肢となりました。開発の内製化やグロース開発を進めたい企業にとって、ラボ型開発は「社外の内製開発チーム」として活用できる柔軟な手法となっています。
ラボ型開発のメリット
ラボ型開発にはさまざまなメリットがあり、ここでは4つの主なラボ型開発のメリットについてご紹介します。
優秀な人材を一定期間確保し、知見を蓄積できる
ラボ型開発では一定期間自社専属の人員およびチームを確保できるため、さまざまな会社やプロジェクトから引く手あまたの優秀な人材を抱え込むことができるというメリットがあります。
また、開発チームにはプロジェクトに特化した知見やノウハウが蓄積されていくため、成果物の品質や開発速度の向上につながります。プロジェクトのたびに毎回必要な人材を探して採用・育成する手間も省けるため、運用の安定化と効率の向上も期待できます。
要望や仕様、優先度などの変更・追加に柔軟に対応できる
ラボ型開発では一定期間自社専属の開発チームを確保するため、契約期間内であれば要求や要望、仕様、優先度などの変更や追加を柔軟に行うことが可能です。請負型開発では必要となる追加見積もラボ型開発では必要がないため、柔軟性に大きな優位性があります。
そのため、プロジェクトの途中で状況が変わりやすい不確実性の高いプロダクトの開発や、臨機応変な対応が必要なアジャイル開発との相性が優れています。
コスト削減効果が期待できる
開発にかかるコストの削減もラボ型開発のメリットの一つです。特に、プロジェクトの総工数が大きくなればなるほどスケールメリットが出るため、コスト削減効果が高まりやすくなります。
また、プロジェクト途中での仕様変更が頻繁に発生しやすい現代の開発現場において、成果物ごとに都度見積や契約が必要となる請負開発型では追加コストや調整による遅延が発生しやすい傾向があります。一方、ラボ型では一定期間にわたって専属チームを確保することから、変更や優先順位の調整に柔軟に対応しやすいため、結果として想定外のコストや調整にかかる時間の無駄を抑えられます。
さらに、ベトナムをはじめとする海外のオフショア開発拠点を活用することで、人月単価そのものの削減も可能です。オフショア開発におけるIT人材の人月単価は国によっても異なりますが、おおむね日本の50%程度が相場となります。近年はオフショアのITエンジニアのスキルレベルや日本語対応能力も向上しており、低コストと品質の両立が実現しやすくなっています。
また、固定メンバーによる継続稼働は、チームの立ち上げや引き継ぎにかかるコストの削減にもつながります。プロジェクトごとにリソースをアサインし直す必要がなく、チーム内での知見蓄積により生産性も向上しやすくなるため、トータルでのコストパフォーマンスが高い点がラボ型開発が企業に選ばれる理由の一つとなっています。
信頼関係とコミュニケーションを強化しやすい
ラボ型開発では、一定期間にわたり同じメンバーと継続的に協働する体制が構築されるため、一般的な外注開発に比べて依頼者側と開発会社側との間で深い信頼関係と円滑なコミュニケーションを築きやすくなります。これにより、細かな仕様のニュアンスや背景意図まで共有しやすくなり、結果として認識の齟齬や手戻りの削減につながります。
また、定例ミーティングやチャットツールを通じて、依頼者側とラボ型開発チームが日常的にコミュニケーションを取る運用が基本となるため、特にアジャイルやスクラムといった開発手法を採用している企業にとっては、外部にいながら社内チームの一部のように動ける柔軟性が大きな魅力です。
さらに、近年はブリッジSEや多言語を扱うPMなど、オフショアでも円滑な意思疎通を支援する人材が増えており、国境や言語の壁を越えたチームビルディングも可能となっています。
こうした環境下で相互の信頼関係が育まれることにより、単なる外注先に留まらず、共に成長する開発パートナーとしての関係性が生まれやすいのも、ラボ型開発ならではの利点といえます。
ラボ型開発のデメリットと対策
ラボ型開発は多くのメリットを持つ一方で、導入・運用にあたっては事前に理解しておくべき課題やリスクも存在します。ここでは主なデメリットとその対策について整理してご紹介します。
稼働状況に関わらず一定のコストが発生するため、割高になることがある
ラボ型開発では「チーム単位での月額契約」が基本であるため、プロジェクトの進行状況や人員の稼働状況にかかわらず一定のコストが発生します。繁忙期と閑散期の波が大きい場合、「人が余る/足りない」といったアンバランスが起こることもあり、仮に確保した人員に対して仕事の量が少ない場合、全体として費用対効果が悪化して割高になる可能性があります。
対策としては、あらかじめ稼働量の見通しを立てて契約期間・人員を計画することが重要です。加えて、一部をスポット契約や変動対応可能な人材と組み合わせることで柔軟性を確保できます。また、QA対応や保守といった業務内容の拡張によってラボ型開発チームの活用幅を広げることで人員の手が空いてしまう無駄な時間が発生しにくくなるため、対策として効果的です。
チームの立ち上げにある程度の時間がかかる
ラボ型開発では依頼者側専属のチームを新たに組成するため、人員の選定からオンボーディング、環境構築、自社に特有の仕事の進め方やルールのインプットなどに一定のリードタイムが必要です。
対策としては、なるべく早期からスモールスタートし、段階的に規模を拡大していくという進め方が有効です。また、PMやブリッジSEといった中心となるポジションにはITの知見に加えてコミュニケーション能力・言語能力に優れた人員をアサインすることで、立ち上げ時の情報共有やナレッジ伝達がスムーズに進みやすくなります。
依頼者側側にも一定のマネジメント力が求められる
ラボ型開発では、仕様書や事前の取り決めに基づいた成果物を納品する請負型開発と異なり、依頼者側が優先度や方向性の意思決定を行う必要があります。そのため、依頼者側にプロダクトオーナーやPMなど、主体的にプロジェクトをリードできる体制が整っていない場合、成果が出にくくなるリスクがあります。
対策としては、依頼者側でプロジェクトの責任者を明確にしたうえで、ラボ型開発チームとスムーズに連携を取ることができる体制を依頼者側に構築することが重要です。また、開発経験やマネジメントに不安がある場合は、伴走型のサポート体制がある開発会社をラボ型開発のパートナーとして選定することで負担やリスクを軽減できます。
コミュニケーションの質が成果に影響しやすい
こちらはデメリットというよりも注意点に近いですが、ラボ型開発では依頼者側とラボ型開発チームとの間での継続的な関係構築が重要となるため、初期のコミュニケーションがうまくいかないと、後々まで信頼関係の欠如や認識のズレが影響を及ぼしてしまうことがあります。
対策としては、定例ミーティングやドキュメント管理ツール、タスク管理ツール、ビジネスチャットツールなど(例:TeamsやSlack、Chatwork、Notion、Jira、Backlogなど)を活用し、非同期でも情報が正確に伝わる環境を整備することが鍵です。特に、重要な情報はテキストでやりとりをすることがおすすめです。また、ラボ型開発の運用が軌道に乗るまでの間は、日次でのミーティングも行うなど可能な限りコミュニケーションの量を増やすことが成功の秘訣として挙げられます。
ラボ型開発が適している案件
ラボ型開発は多くの場合に有効な開発手法ではあるものの、特定の条件やフェーズにおいて特に大きなメリットを発揮します。ここでは、ラボ型開発が適している案件の特徴について解説します。
要件や仕様が変わりやすいプロジェクト
SaaSやWebアプリ、モバイルアプリなどの、ユーザーの反応や市場の変化に応じて仕様変更や機能追加が頻繁に発生するようなプロジェクトには、ラボ型開発が適しています。
このようなプロジェクトは、請負型では都度見積が発生するため対応が難しく、柔軟に開発内容を調整できるラボ型の方がスムーズに開発を進めることができます。
中長期的な継続開発が前提のプロダクト
リリース後も機能追加や改善、保守運用が続くプロダクトでは、ナレッジを継続的に蓄積できる開発体制が重要です。
ラボ型開発では同じメンバーが長期にわたってプロジェクトに参加するため、属人性を抑えながら継続性を保ちやすいのが特徴です。特にプロダクトのライフサイクルが長いプロジェクトや、複数機能の段階的リリースが必要な場合に大きな効果を発揮します。
アジャイル開発やスクラムを採用するプロジェクト
変化に対応しながら短いサイクルで反復的にリリースを繰り返すアジャイル開発やスクラムを採用しているプロジェクトでは、固定されたメンバー・チームでの継続的な協働が欠かせません。
ラボ型開発は、契約上も運用上もアジャイルやスクラムといった開発スタイルと相性がよく、開発メンバーが仕様やユーザーに対する理解を深めながら継続的に精度や生産性、品質を高めていくことが可能です。
定期的な業務が発生する案件
定期的な発注や継続的な作業が発生する案件は、ラボ型開発との相性が非常に良いと言えます。ラボ型開発は一定期間同じ開発チームが継続的にプロジェクトに関わるため、業務知識や技術的なノウハウが蓄積され、対応の質とスピードが向上します。
さらに、こうした定期業務に対してオフショアのラボ型開発を活用することができれば、対応体制を維持し一定の品質を保ちながらコストの最適化が可能になります。
ラボ型開発と請負型開発との違い
ラボ型開発と請負型開発は多くの点で対照的ですが、ラボ型開発と請負型開発の主な違いをまとめると以下のようになります。
| 観点 | 請負型開発 | ラボ型開発 |
| 契約形態 | 請負契約 | 準委任契約 |
| 契約対象 | 完成物・成果 | 専属チーム (人×期間) |
| 変更への耐性 | 低い (変更は別契約・都度見積) |
高い (仕様変更に強い) |
| 知見の蓄積 | されにくい | されやすい (チーム単位で蓄積) |
| 依頼者側の マネジメント負荷 |
低い | 中~高 (主体的な関与が必要) |
| 適している案件 | 範囲や納期、仕様が固定 | アジャイル開発や継続改善が前提 |
上の図のように、ラボ型開発は硬直性が高い請負型開発とは対照的に、専属チームを確保しての運用となるため継続的な開発や改善に最適です。
また、繰り返しになりますが、ラボ型契約の契約形態は期間ベースの準委任契約が一般的であり、特にアジャイル開発と相性が良いという特徴があります。
ラボ型開発の費用
ラボ型開発にかかる費用は、基本的には「契約する人数×役割別の人月単価×契約期間」という形で計算されます。
ここでは例として、開発エンジニア2名(人月単価50万円)、テストエンジニア1名(人月単価40万円)、プロジェクトマネージャー0.3名(人月単価60万円)という体制で、3ヵ月間契約した場合のラボ型開発の費用は以下のようになります。
※プロジェクトマネージャーやブリッジSEなどは、1ヵ月あたり0.2~0.5名程度で案件にアサインされることが一般的です。
- 開発エンジニア:2名×50万円×3ヵ月=300万円
- テストエンジニア:1名×40万円×3ヵ月=120万円
- ブリッジSE:0.3名×60万円×3ヵ月=54万円
- 合計:474万円
※場合によっては、上記に固定費や共通費などが加わるケースもあります。
参考までに、ベトナムのオフショア開発会社のラボ型開発を利用した場合の役割別の人月単価の相場としては、プログラマーが約39万円、シニアエンジニアが約48万円、ブリッジSEが約59万円、プロジェクトマネジャー(PM)が約70万円となっています。
ラボ型開発の成功のポイント
ラボ型開発は、適切に運用すれば優れた柔軟性・コスト効率・品質を実現できる開発手法ですが、その成果を最大化するには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。ここでは、ラボ型開発を成功に導くための5つのポイントについてご紹介します。
スモールスタートと段階的な拡張
初期から大規模な体制で始めるのではなく、まずは1〜2名の小規模なチームからスタートし、成果やコミュニケーションの手応えを確認しながら段階的に拡張するアプローチがラボ型開発にはとても効果的です。
これにより、ミスマッチや無駄なコスト発生を抑えつつ、スムーズに信頼関係と運用フローを構築しながら規模を拡大していくことが可能となります。
継続的なコミュニケーションとフィードバック
ラボ型開発では、一定期間にわたって同じメンバー・チームで継続的に協業するため、信頼関係の構築と日常的なコミュニケーションが非常に重要です。週次の定例ミーティングやチャットツールを通じたやり取りを習慣化し、こまめなフィードバックや情報共有を行うことで、チームの理解度と自走力が高まります。
ナレッジの蓄積と可視化
成功するラボ型開発では、開発チームに情報が属人化しない仕組みが整っています。タスク管理ツールやドキュメント共有ツールを活用し、仕様・設計・開発フローなどを常に可視化しておくことで、メンバー交代やチーム拡張にも柔軟に対応できます。
また、振り返りやレビューの習慣を持ち、チーム内に学びが残るサイクルをつくることも大切です。
依頼者側の主体性とリーダーシップ
ラボ型開発は請負型開発のように「事前の取り決め通りの納品」を前提とする契約ではなく、依頼者側が開発の方向性や優先順位をリードするモデルです。そのため、依頼者側にプロダクトオーナーやPMがいない、あるいは判断が遅いと、ラボ側の開発チームの稼働効率が下がり期待する成果が得られにくくなります。
ラボ型開発を成功させるためには、開発をリードできる人材を依頼者側に確保し、意思決定・仕様整理・優先順位づけを明確に行う体制が極めて重要となります。
信頼できるパートナー選び
いくら内部体制を整えても、パートナーとなる開発会社の技術力や姿勢、対応力が不足していては、成果につながりません。ラボ型開発においては、技術力に加えて、マネジメント能力や提案力、対応のスピード・柔軟性、PMやブリッジSEといった管理層の厚さ、自社との文化的相性などを含めて慎重に選定することが重要です。
特に、自社のラボ型開発チームに日本人PMやコミュニケーション力・技術力の両方に優れたブリッジSEをアサインできるかどうかによって難易度が大きく変わるため、日本人PMとブリッジSEの数やレベルについては必ず確認しましょう。
また、なるべく自社の業界やプロダクトに近い領域での実績や事例があり、立ち上げフェーズから伴走支援してくれるラボ型開発パートナーを見つけることが成功への近道です。
まとめ
ラボ型開発は、柔軟な仕様変更への対応力、継続的なチーム運用によるノウハウ蓄積、そしてコスト効率の高い体制構築を実現できる開発手法です。特に、新規の立ち上げやグロースフェーズにあるプロダクト、継続的な改善が求められるシステム、定期的な業務が発生する案件などにおいて、その効果を最大限に発揮します。
一方で、依頼者側のマネジメント力や、初期設計・運用体制が成果に直結するため、依頼者側・開発会社側が一丸となって成果を出すという意識や体制、準備が成功のポイントとなります。信頼できるパートナーを選び、中長期的な視点でチームを育てていくことで、単なる外注を超えた共創型の開発体制を築くことができるでしょう。
変化の早い市場環境において、スピードと柔軟性を両立させるラボ型開発は、今後ますます重要な選択肢となっていくはずです。
ラボ型開発で、強力な開発体制を構築したい企業さまへ
わたしたちSHIFT ASIAは、ソフトウェア品質保証・第三者検証のリーディングカンパニーである株式会社SHIFT(プライム市場上場)の海外戦略拠点として、ベトナム・ホーチミンにてオフショア開発・ソフトウェア開発およびソフトウェアの品質保証事業を推進しています。
SHIFT ASIAでは、IT人材不足を解決する手段として海外の優秀なエンジニア層を活用しながら、日本のお客様のニーズに応えるべく優秀なベトナム人エンジニアの採用と育成に力を入れています。また、ベトナム現地にIT経験豊富な日本人スタッフ約20名が在籍しており、お客様とのコミュニケーションやプロジェクトマネジメントなど、日本の開発現場と遜色ない環境を提供しています。
ラボ型開発においては「最小1名・1ヵ月から」短期間でのスモールスタートが可能なソリューションをご提供しており、リスクを抑えたラボ型開発が可能です。
SHIFTグループで培われた開発やテストのナレッジと、1,000を超えるオフショアプロジェクトの実績を活かし、日本と同等以上の価値をリーズナブルな価格でご提供いたします。
ラボ型開発をはじめ、オフショアでの開発やテストに関してお悩みやお困りごとなどがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
>>ソフトウェア開発ソリューションのページへ
>>ソフトウェア開発ソリューション紹介資料のダウンロードページへ
>>オフショア開発会社選定ガイドのダウンロードページへ
>>導入事例ページへ
>>お問い合わせページへ
お問い合わせContact
ご不明点やご相談などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。