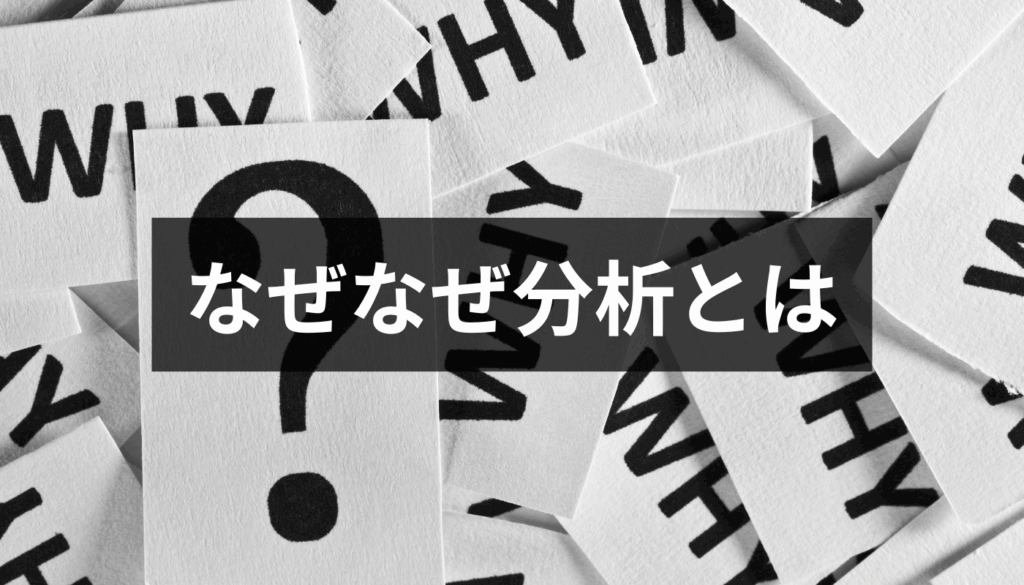なぜなぜ分析は、問題が発生した際に「なぜ?」という問いを繰り返すことで、表面的な原因だけでなく根本的な原因(真因)を明らかにし、本質的かつ効果的な解決策を導き出す問題解決手法です。
なぜなぜ分析はトヨタ生産方式の中で生まれたこともあり、当初は主に製造業で取り入れられ始めましたが、現在ではIT業界やサービス業など幅広い分野で活用されています。
本記事では、なぜなぜ分析の概要から目的やメリット、具体的なやり方、成功させるためのポイント、陥りやすい失敗例とその対策までをわかりやすく徹底解説します。
本記事の内容を通じて、皆さまの問題解決力の向上に少しでも貢献することができれば幸いです。
なぜなぜ分析とは
なぜなぜ分析は、問題が起きたときに「なぜその問題が起きたのか?」を繰り返し問い続けることで、問題の根本原因(ルートコーズ)・真因を特定する問題解決手法です。
一般的には「なぜ?」を5回繰り返すことが目安とされており、これにより表面的な原因からより深く踏み込んだ本質的な原因を探ります。「なぜ?」を繰り返す回数の目安が5回であることから、なぜなぜ分析は英語では「Five whys (5 whys)」と呼ばれます。
なぜなぜ分析はトヨタ生産方式のなかで用いられ、製造現場での問題解決に大きな効果を上げたことから注目を集めました。今や、なぜなぜ分析は業種や業界を問わず、また日本だけでなく世界中にまで広まっています。
なぜなぜ分析が業界を問わず世界中で活用される理由
問題解決において重要なことは、根本的な原因である真因を見つけて適切に対策を講じることにあります。もし問題の表面だけしか解決されなかった場合、結局のところ真因は残ったままとなるため、再発のリスクが高い状態となるためです。
なぜなぜ分析は、「なぜ?」という問いかけを何回も繰り返して問題を掘り下げていくというアプローチをとるため、本当に問題を解決するための原因特定に非常に有効です。
また、なぜなぜ分析は他の問題解決手法と比べてシンプルで誰でも実践しやすい点も特徴です。必ずしも複雑な分析ツールを使う必要もなく、自分一人だけですぐに実施することも可能です。
さらに、なぜなぜ分析は個人で行うだけでなく、チームで議論しながら進めることで、多角的な視点を取り入れ、より効果的な原因特定と対策立案が可能になります。これにより、組織内でのコミュニケーションが活発となり、知見の深化や学習・成長の促進にもつながります。
なぜなぜ分析の活用事例
なぜなぜ分析は、上で述べたように、その汎用性の高さから様々な業界で活用されています。
製造業での活用例
トヨタ生産方式から生まれたように、製造業では不良品発生、機械トラブル、労働災害といった問題の根本原因究明に広く用いられています。
例えば、「製品の異物混入」に対して、その原因を「なぜ異物が入ったのか」「なぜ検査で発見できなかったのか」と深掘りし、設備の問題や作業手順の不備、教育体制の不足といった真因にたどり着きます。
IT業界やサービス業での活用例
顧客からのクレームやシステム障害、プロジェクトの遅延など、サービス品質や業務効率に関わる問題解決にも活用されます。
例えば、「システムが頻繁にダウンする」という問題に対し、「なぜダウンするのか」「なぜ設計段階で考慮されていなかったのか」と問いを重ねることで、開発プロセスの問題やテスト不足、要件定義の甘さといった根本原因を特定します。
なぜなぜ分析のメリット
なぜなぜ分析は、問題の根本原因を明らかにし、効果的な対策を導き出すためのシンプルながら強力な手法です。ここでは、なぜなぜ分析を導入・活用することで得られる具体的なメリットについて、最新の知見を踏まえて詳しく解説します。
根本原因の特定による効率的な問題解決
なぜなぜ分析は、問題の表面的な症状だけにとどまらず、根本原因・真因を深掘りすることができます。これにより、単なる対処療法ではなく、再発を防止するための本質的な解決策を立てられます。
たとえば、あるシステムが停止した場合、表面的には「システムの故障や不具合」が原因とされがちですが、なぜなぜ分析を通じて「メンテナンス不足」や「実装時の不備」、「設計時の仕様間違い」などの根本原因を特定できれば、同じトラブルを繰り返さずに済みます。これにより、問題解決にかかる時間やコストの削減、さらにはムダの排除が実現します。
リスク管理と再発防止の強化
なぜなぜ分析は、問題発生後だけでなく、潜在的なリスクの洗い出しや未然防止策の策定にも活用できます。根本原因・真因を特定し、効果的な予防策を講じることでリスクを低減し、組織の安定運営を支えます。
特に品質管理や安全管理の分野では、なぜなぜ分析を通じて再発防止策を確実に実施することが、重大な事故やクレームの防止に直結します。
組織全体の問題解決能力と学習効果の向上
なぜなぜ分析は、単独の作業ではなく、関係者やチームで実施することが多いため、組織内のコミュニケーション活性化や情報共有の促進に寄与します。問題の原因や対策を共有する過程で、メンバーの理解が深まり、組織全体の問題解決力が向上します。
また、常に「なぜ?」と問う習慣づけや分析の経験を積み重ねることで、従業員一人ひとりが問題に対して主体的に考える文化が醸成され、業務改善の意識向上やモチベーションアップも期待できます。
製品・サービスの品質向上と顧客満足度のアップ
問題の根本原因・真因を解消し、業務プロセスを改善することで、製品やサービスの品質向上が期待できます。これにより、顧客からの信頼が高まり、顧客満足度の向上やブランド価値の強化につながるのです。
例えば、顧客からのクレームをなぜなぜ分析で深掘りし、サービス提供の仕組みを改善すれば、同様のクレームの再発を防ぎ、顧客ロイヤルティの向上にもつながります。
幅広い業種・業務での活用が可能な汎用性
なぜなぜ分析はもともと製造業で発展した手法ですが、そのシンプルさと効果の高さから、IT、サービス業、プロジェクトマネジメント、マーケティングなど多様な分野で活用されています。
業務の遅延、品質問題、顧客対応、プロジェクトの課題抽出など、あらゆる問題に対して適用できるため、組織の問題解決基盤として幅広く支持されています。
なぜなぜ分析のやり方・手順
なぜなぜ分析は、問題の真因を特定し、効果的な解決策を導き出すために「なぜ?」を繰り返すシンプルな手法ですが、ここでは具体的な分析のやり方・手順について解説します。
ステップ1:問題の明確化
まず、解決したい問題を具体的に定義します。問題を解決するための前提として、「本当に解くべき問題」を見極めることが非常に重要であり、問題が抽象的だったり間違ったものであったりすると分析がうまく進みにくく、また意味のある対策になりません。
ポイントとしては、例えば「顧客データの処理時間が、先月の平均値と比較して10秒遅延している」のように、何を、どれくらい、どのように、といった具体的な情報を含めることが重要です。また、関係者全員が同じ問題認識を持つことが効果的な分析の出発点となります。
ステップ2:「なぜ?」を繰り返し問いかける
定義した問題に対して、「なぜ?」を繰り返し問いかけ、原因を深掘りしていきます。一般的には5回「なぜ?」を繰り返すことが目安とされていますが、根本原因にたどり着くまで問い続けることが重要です。必ずしも5回という回数にこだわる必要はなく、5回未満でも真因と思われる原因にたどり着くことができればそこで「なぜ?」をやめても問題なく、同じように「なぜ?」を5回繰り返しても真因が見えてこない場合は、さらに「なぜ?」を繰り返すべきです。
また、問いかけを繰り返す際には、問題とそれに対する「なぜ?(=原因)」を図示し、関係性を可視化することも効果的です。
問題:「システムが停止した」
- なぜ?:「サーバーが停止したから」
- なぜ?:「システムに負荷がかかりすぎたから」
- なぜ?:「適切な設計がされていなかったから」
- なぜ?:「要件における処理能力や同時接続数が小さすぎたから」
- なぜ?:「処理能力や同時接続数に関する社内規定が存在しなかったから」
問題の原因が一つとは限らないため、複数の可能性が考えられる場合は、枝分かれさせて原因を究明することも重要です。
ステップ3:根本原因の特定と対策立案
「なぜ?」を繰り返して得られた結論をもとに、問題の根本原因(真因)を特定します。この段階で原因が明確にならない場合は、追加の調査や再度「なぜ?」を行うことも必要です。
そして、特定された根本原因に対しての具体的な対策を立てます。対策は、実行可能で実際に効果が期待できるものを選ぶことが重要です。
ステップ4:対策の実行と効果の検証
立案した対策を実行に移し、その効果を検証します。問題が完全に解決されたかを確認し、必要に応じて追加の対策を講じます。
真因は正しくても対策が不十分な場合もあるため、その際は対策の改善を行います。
なぜなぜ分析を成功させるコツと注意点
なぜなぜ分析を効果的に行うためにはいくつかの重要なポイントがありますので、こちらで詳しく紹介します。
解決したい問題を明確かつ具体的にしておく
分析の出発点は「解決すべき問題の正確な把握」です。問題が曖昧な状態では、原因の掘り下げが具体的になりにくく、効果的な対策が立てられません。
「製造ラインの停止」ではなく、例えば「2025年6月に製造ラインが3回停止し、合計2時間の稼働停止が発生した」など、具体的な事象や数値を盛り込み、誰が見ても理解できる形にすることが重要です。
また、問題の背景や影響範囲も整理し、分析の前提条件をチームで共有することにより、分析の方向性がぶれにくくなります。
客観的かつ多角的な視点で分析を進める
感情や推測を排除し、事実に基づく検証を重視しましょう。データや現場の状況を確認しながら進めることで、誤った結論を避けられます。また、関係者や現場担当者を巻き込み、多様な視点を取り入れることも重要です。複数の意見を集めることで、見落としや偏りを防ぎ、深い理解につながります。
問題が複雑な場合は要素ごとに分解し、個別に掘り下げていきましょう。複数の原因が絡む場合は、因果関係を整理しながら分析を進めることが有効です。
「なぜ?」の問いは、因果関係を意識して連鎖的に掘り下げる
単発の「なぜ?」で終わらせず、前の原因に論理的につながる問いを繰り返すことで、表面的な理由から根本原因へと段階的に掘り下げられます。
また、5回という回数にこだわらず、根本原因が明確になるまで継続することが重要です。必要に応じて5回以上問いかけることもあります。
個人の責任追及に陥らず、仕組みやプロセスに着目する
「人のミス」だけに原因を求めないことが重要です。多くの場合、人的ミスは仕組みや環境の問題が背景にあります。組織全体の改善を目指しましょう。
また、心理的安全性を確保し、責めるのではなく建設的な議論を促しましょう。現場の本音や事実を引き出しやすくなり、分析の精度が上がります。
実行可能で具体的な対策を立案し、責任と期限を明確にする
表面的な対応をとるのではなく、根本原因に直結した再発防止策を考え、問題の本質を解消することが重要です。また、対策を立案しただけで終わらせず、対策の担当者や実施期限を明確にし、実行とフォローアップ、進捗管理を確実に行いましょう。
対策の効果検証と継続的な改善を実施する
対策実施後は必ず効果を評価し、本当に問題が解決されているか確認しましょう、効果が不十分な場合は、あらためて分析を行い対策の見直しを行います。
また、PDCAサイクルの一環として継続的に改善活動を推進することで、問題が起きてもすぐに原因特定と解決を進める社内文化の形成にもつながります。
分析結果の記録と共有を徹底し、組織の知見として蓄積する
分析の過程や結論、対策をドキュメントとして残し、関係者で共有しましょう。これにより、類似の問題発生時の対応が迅速かつ効果的になります。また、ナレッジマネジメントの一環として活用することで、組織全体の問題解決力の向上も期待できます。
なぜなぜ分析における、よくある失敗例とその対策
なぜなぜ分析はシンプルで強力な問題解決手法ですが、誤った進め方をすると根本原因にたどり着けず、再発防止にもつながりません。ここでは、実務現場で頻発する失敗パターンと、それを防ぐための具体的な対策を詳しく解説します。
問題の定義が曖昧なまま始めてしまう
失敗例:
「納期遅れが発生したのはなぜか?」といった抽象的な問いから始めてしまい、原因も曖昧なまま分析が進む。
問題の発生日時や影響範囲、具体的な状況が整理されていない。
対策:
問題は「いつ・どこで・誰が・何を・どのように」など、5W1Hで具体化する。
例:「2025年6月10日、Aラインで生産した製品Bが、検査工程で不良率10%を記録したのはなぜか?」のように、誰が見ても状況がイメージできる形で定義する。
原因追及が個人責任に終始する
失敗例:
「担当者が確認を怠った」「Aさんがミスした」といった、個人の行動や能力に原因を押し付けてしまう。
分析が「誰のせいか」を探す責任追及になり、仕組みやプロセスの改善につながらない。
対策:
「なぜ担当者がミスに気付けなかったのか」「なぜミスが発生しても検知できなかったのか」と、組織や仕組みの観点で深掘りする。
「この問題は他の人でも起こり得るか?」と問い直し、個人ではなく全体の仕組みや環境に目を向ける。
因果関係が不明瞭なまま進めてしまう
失敗例:
各「なぜ?」の答えが前の問いと論理的につながっていない。
「なぜ?」の連鎖が飛躍してしまい、原因が枝分かれして収拾がつかなくなる。
対策:
各段階で「この答えは前の問いの直接的な原因か?」を必ず確認する。
必要に応じて図や表を使い、因果関係を可視化しながら進める。
想像や憶測で原因を決めてしまう
失敗例:
現場の事実確認をせず、経験や思い込みで「たぶんこうだろう」と原因を決めてしまう。
データや証拠に基づかない分析となり、的外れな対策につながる。
対策:
必ず現場の状況やデータを確認し、客観的な事実に基づいて分析を進める。
関係者へのヒアリングや現場・現物・現実(三現主義)の徹底を意識する。
対策が抽象的・実行不可能で終わる
失敗例:
「注意喚起を徹底する」「ミスをなくす」といった抽象的な対策で終わる。
実際の行動や仕組みの改善につながらず、再発防止ができない。
対策:
「何を・誰が・いつまでに・どのように」実施するかまで具体化する。
例えば「作業手順書を改訂し、全員に再教育を実施。6月末までに完了」など、実行可能な内容に落とし込む。
分析や対策が記録・共有されない
失敗例:
分析結果や対策が口頭だけで済まされ、記録や共有がされていない。
同じ問題が発生した際に過去の知見が活かされない。
対策:
なぜなぜ分析の過程と結果、対策内容をテンプレートや議事録に記録し、関係者で共有する。
ナレッジとして蓄積し、類似問題の再発防止や迅速対応に活用する
まとめ
なぜなぜ分析は、「なぜ?」を繰り返し問いかけることで問題の根本原因を特定し、再発防止策を導き出す強力な問題解決手法です。トヨタ生産方式に端を発し、現在では世界中で様々な業界において活用されています。
本記事では、なぜなぜ分析の概要、目的、メリットから、具体的なやり方、成功させるためのポイント、陥りやすい失敗とその対策までを具体的に解説しました。
なぜなぜ分析を効果的に活用することで、企業としても個人としても、問題解決能力を高め、業務効率を向上させ、最終的には顧客満足度の向上と持続的な成長を実現することができます。ぜひ、本記事を参考に、日々の業務に「なぜなぜ分析」を取り入れ、真の問題解決に挑んでみてはいかがでしょうか。
SHIFT ASIAについて
私たちSHIFT ASIAは、ソフトウェア品質保証・第三者検証のリーディングカンパニーである 株式会社SHIFT(プライム市場上場)の海外戦略拠点として、ベトナム・ホーチミンにてソフトウェアテスト事業を手掛けながら、オフショア開発・ソフトウェア開発にも事業領域を拡大させてきました。長年に渡り培ってきた品質保証のナレッジとハイレベルなエンジニアの技術力を背景とした、高品質かつスピーディな開発をその特長としています。
ソフトウェア開発やテストでお困りのことがありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせContact
ご不明点やご相談などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。