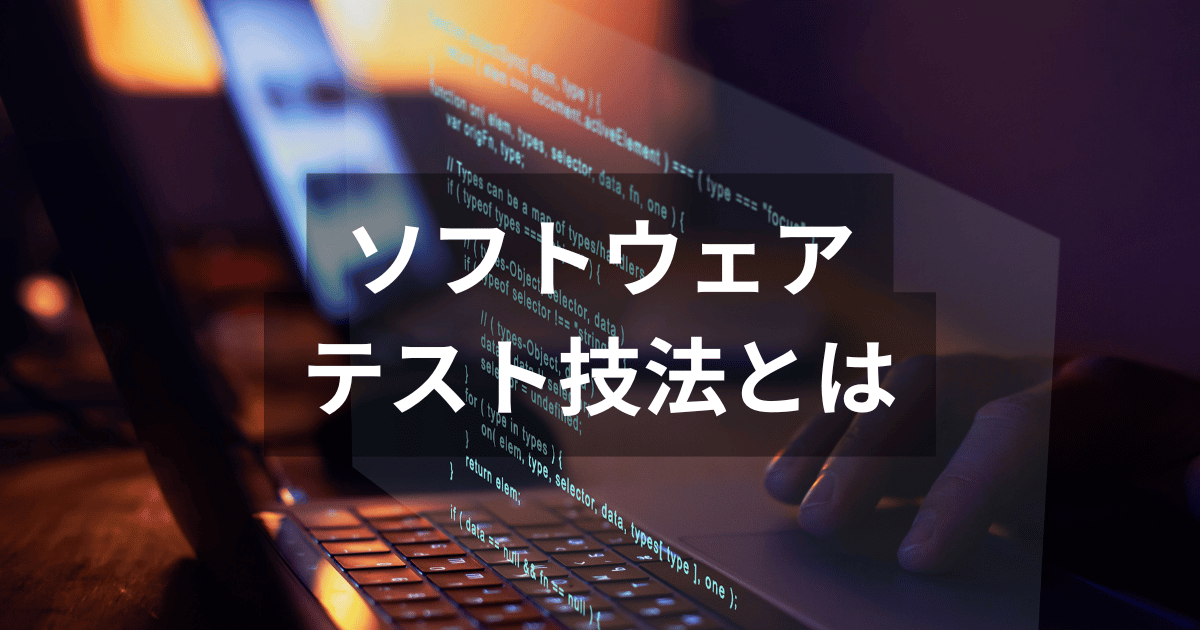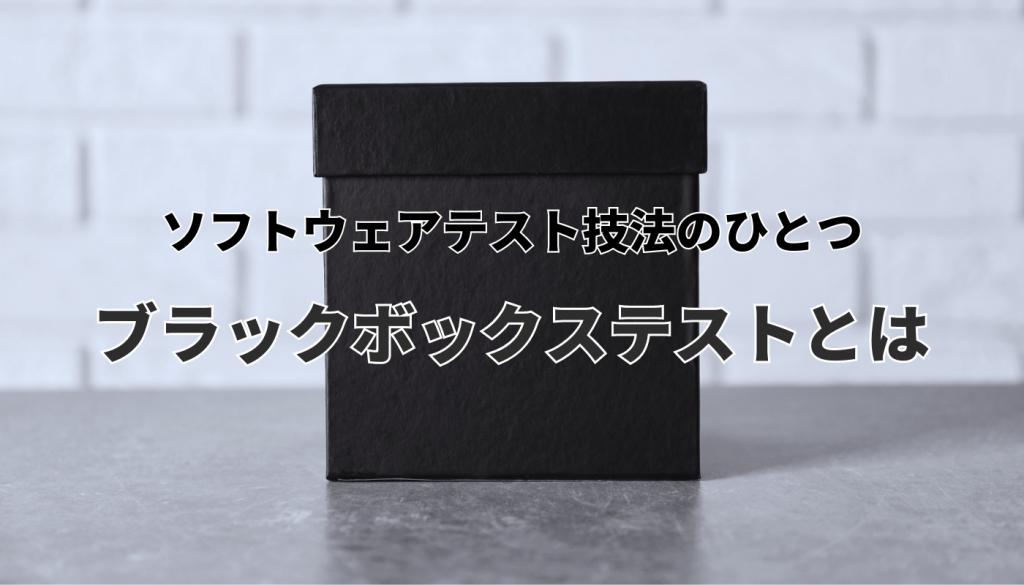探索的テストとは
探索的テスト(Exploratory Testing)とは、テスト担当者が「テスト対象のプロダクトと欠陥の学習」「テストの計画」「テスト内容の設計・実行・評価」を並行して行う、ソフトウェアテストの1つのスタイルです。
事前にテストケースを設計せず、テスト実行の過程や結果を通じてテストの目標や内容を動的に調整し、積極的に質の高い新しいテストケースを設計していくという特徴があります。
テスト対象の振る舞いに着目し、そのフィードバックを元にテスト内容を改善していくことから、「対話型」のアプローチといわれることもあります。
事前にテスト設計を行う必要がないことから、必ずしも仕様書や設計書といったドキュメントを必要とせず、また同様の理由から事前に準備がかからずスピーディーに実施できることから、特にアジャイル開発と相性が良いとされています。
近年では開発手法としてアジャイル開発が取り入れられるケースが増えていることから、探索的テストに対する注目度が高まっています。
アドホックテストとの違い
探索的テストと「アドホックテスト」「モンキーテスト」は混同されがちですが、両者は明確に異なります。
「アドホック」とはラテン語で「その場限りの」「特定の目的のための」といった意味をもち、アドホックテストとは場当たり的に思いついたテストを実施することを指します。
アドホックテスト(モンキーテスト)については、『アドホックテスト(モンキーテスト)とは|短期間・低コストで品質を底上げ』の記事で紹介していますので、ぜひ合わせてご参照ください。
一方で探索的テストの場合は、テストの過程でテスト対象からのフィードバックをもとに目標や内容を動的に変更・改善していくという特徴から、場当たり的な「アドホックテスト」「モンキーテスト」とは一線を画します。
記述式テスト(スクリプトテスト)との違い
また、探索的テストと従来の記述式テスト(スクリプトテスト)には以下のような違いがあります。
「記述式テスト(スクリプトテスト)」では、設計書や仕様書といったドキュメントをインプットとし、それをベースにテスト設計を行いテスト仕様書を作成した上で、実行者はテスト仕様書のテストケースにもとづいてテストを実行します。
記述式テストのアプローチでは、仕様に対して網羅性の高いテストが実施でき、またテストケースにもとづいてテストを進めることから個人のスキルに左右されず、属人性が取り払われるというメリットがあります。
その一方で、事前にテストケースを準備する必要があることからその分の時間やコストを要することや、テストケースに沿って機械的にテストを実行することから、不具合が見つかる可能性が低いテストまで行う必要があったり、テストの最中で実行者が得た気づきをテスト内容に反映しにくいというデメリットがあります。
探索的テストはこの真逆のアプローチといえます。
上で述べたように、探索的テストでは事前にテストケースを準備せず、テスト担当者が自身の経験・学習を通じて「属人的」にテストを実施し、その結果に応じて柔軟にテスト内容を変更していくアプローチです。
ゆえに、探索的テストと記述式テストは相互に補完的な関係にあるといえます。
探索的テストのメリット・デメリット
探索的テストにも記述式テストと同様に、メリットだけでなくデメリットも存在します。
実際のテストにおいては、探索的テストのメリット・デメリットを明確に認識した上で運用する必要があることから、主なメリットとデメリットについてこちらで紹介いたします。
探索的テストのメリット
1.スピードの速さ
記述式テストと異なり、事前にテストケースを用意する必要がないことから、テスト設計やレビュー・修正といった工程が必要ありません。テストケースの準備には実行以上に時間を要することも多く、その工程を省くことができるのは大きな時間的なメリットとなります。
またテストの過程で目標や内容を変更する必要が生じた場合でも、必ずしも逐一ドキュメントを作成する必要がないことから、実行自体もスピード感をもって行うことができます。
さらに事前準備は最低限としてスピーディーに開始することができるため、不具合が検出されるタイミングも早くなる傾向にあります。これはテスト対象の品質を素早く向上することにも役立ちます。
このことから網羅性よりもスピードを重視する場合に特にメリットが大きく、アジャイル開発と相性が良いと言われる1つの理由となっています。
2.工数・コストを抑えやすい
上で述べたようなドキュメントの作成や事前準備を最低限として実行・改善をハイスピードでまわすことができる上、テスト担当者のスキルや判断に左右されるものの、より効果的な部分にフォーカスしてテストを行うことができることから、記述式テストに比べて工数・コストを抑えやすいアプローチといえます。
またテストにおいて意外と見逃されがちなコストとして「コミュニケーションコスト」がありますが、探索的テストは基本的に個人のテスト活動であることから、コミュニケーションコストの抑制にもつながります。
3.仕様書や設計書といったドキュメントが無い/不十分な状態でも実施可能
探索的テストはテスト対象のみをインプットとしても実施可能なことから、ISTQBによれば「仕様がほとんどなかったり、不十分であったりする場合に最も効果が大きい」といわれています。
このことからも、仕様が未確定であったり、ドキュメントとして存在していない場合であってもテストが実施でき不具合を検出できるという点は大きなメリットです。
アジャイル開発では仕様がドキュメントに十分に記載されていないことや、そういったドキュメント自体が存在しないという場合もあることから、メリット1と同様にアジャイル開発と相性が良いと言われる理由の1つとなっています。
4.記述式テストでは検出困難な不具合を見つけやすい
探索的テストでは、実行の結果・システムの振る舞いというフィードバックをもとにその場で新たなテストケースを設計(必ずしもドキュメント化する必要はなく、頭の中で行われるケースも多い)し実行を進めていきます。
その特性上、テストケースとしては用意しにくいような部分のテストができ、結果として記述式テストでは検出困難な不具合を見つけやすいというメリットがあります。
5.「殺虫剤のパラドックス」を回避しやすい
同じテストを何度も繰り返すと、最終的にはそのテストでは新しい欠陥を見つけられなくなることを「殺虫剤のパラドックス」と呼びますが、これはテストの過程で見つかった欠陥がその都度修正されるために起こります。
従来のテスト手法では、テストの範囲や観点を固定して行うことが多いため、「殺虫剤のパラドックス」を避けるためには、これらを意識的に調整しなければなりません。
ソフトウェアテストの原則5 | 殺虫剤のパラドックスにご用心
しかし、探索的テストでは、テスト担当者がテストを進めながらその内容を動的に調整していくため、テストの範囲や観点が固定されにくくなっています。この動的な調整によって、新しい視点や方法でテストが行われやすくなります。
その結果として、探索的テストでは「殺虫剤のパラドックス」を自然に避け、より多くの新しい欠陥を見つける機会が増えるというメリットがあります。
探索的テストのデメリット
1.属人性が極めて高い
探索的テストは基本的に個人のテスト活動であることから、テストの内容やアウトプットはテスト担当者の経験やスキルに極めて高く依存します。
また貴重なインプットとなる実行の結果における「気づき」には偶然性が高く、実行スピードもテストケースをベースとしたテストに比べると安定しにくいことから、アウトプットの品質にムラが生じやすいという傾向があります。
ゆえに探索的テストを実施する際には、テスト対象に対する深い知識と豊富なテスト経験を有するテスト担当者をアサインすることが重要です。
2.網羅性の担保ができない
探索的テストでは事前に具体的に何をどうテストするかといったことを厳密に定義することができず、また実行の最中においてテストケースが作成されないことも多いことから、テストの結果どの程度の網羅性が担保されたかの判断ができません。
このことは、「探索的テストだけでは品質保証ができない」ということを意味します。
例えば「この機能のこの範囲に対して、こういった前提のもとこういった観点でこういったテストをしたことから、こういった手順・操作での不具合は発生しないことを保障します」の積み重ねが品質の保証だとすると、探索的テストの場合はテストを行った内容自体はブラックボックス化されることから、テストを終えた後に何が担保できるか・保証できるかを明確にエビデンスをもって説明することができません。
ゆえに不具合の検出ではなく「品質保証」を目的とする場合は、記述式テストなど他のテスト手法を組み合わせて実施する必要があります。
3.仕様バグをテスト前に検出できない
従来の記述式テストでは、テストの設計段階でテスト対象の仕様書(設計書)をもとにしてテストを緻密に構築します。この設計過程で仕様書に含まれる矛盾や抜け漏れといった間違いを検出することができ、それによって仕様段階での不具合(仕様バグ)を早期に見つけることが可能です。
仕様段階で不具合を検出できれば不具合が実装される前に修正することができ、修正コストを飛躍的に削減することができます。
一方、探索的テストでは、事前に詳細なテスト設計を行いません。そのため、探索的テストは仕様バグをテスト前に検出するという点ではその効果が期待できません。
4.管理・コントロールが難しい
探索的テストは基本的に厳密なテスト計画やテスト設計を行わないことから、管理者が実施されるテストの量や質、範囲をコントロールしにくいというデメリットがあります。
このデメリットに対応するために、探索的テストの中にも様々な手法が存在しています。
そこで続いては、探索的テストの代表的な3つの手法について紹介します。
探索的テストの3つの手法
探索的テストにはさまざまな手法がありますが、ここでは代表的な手法である「フリースタイルの探索的テスト」「テストチャーターを用いる探索的テスト」「セッションベースドテスト」の3つの手法についてそれぞれ紹介します。
フリースタイルの探索的テスト
フリースタイルの探索的テストは、3つの探索的テストの手法の中で最も自由度が高い手法です。フリースタイルの探索的テストでは、テストの目的や範囲、時間などを厳密には設定しません。
そのため、テスト活動はテスト担当者のスキルや経験に大きく依存しますが、テストの実施中に得られる洞察や学習を基に自由にテストを進めることができます。
フリースタイルの探索的テストでは、テスト担当者は似た製品で不具合が生じやすい箇所や、テスト中に不具合の発生を予感させる箇所を特定し、重点的かつ柔軟にテストを行うことも可能です。このようなアプローチにより、テストの自由度が非常に高くなる一方で、担当者の属人性も高まります。
そのため、この手法を効果的に活用するためには、テスト対象や関係するドメインに対する深い知識と豊富なテスト経験を持つテスト担当者が実施することが望ましいといえます。
テストチャーターを用いる探索的テスト
テストチャーターを用いる探索的テストは、事前にテストの指針を決めて探索的テストを行う手法です。
一般的に、テストチャーターとはテストの目的およびその目的を達成するためのテスト方針を記したものであり、「何をテスト対象とするか」「それをどのようにテストするか」「どのような不具合を見つけたいか」といった項目が記載されます。また、場合によっては抽象度の高いテストケースをチャーターに取り入れることもあります。
テストチャーターはあくまでもテストの指針であり、その内容を細かく記しすぎないことが重要です。細かく設定しすぎると記述式テストに似てしまい、探索的テスト特有の柔軟性や自由度を損ねる危険があるためです。
テストチャーターを活用することでテストの内容やそれによって得られる成果をある程度コントロールでき、計画的かつ効率的に探索的テストを進めることが可能になります。これにより、テスト担当者は自由と指針の間でバランスを保ちながら目的達成に向かって柔軟にアプローチしやすくなります。
セッションベースドテスト
セッションベースドテストは、あらかじめ設定された時間枠(セッション)のなかで探索的テストを行う手法です。また、同時にテスト目的を含むテストチャーターに従ってテストを実施するため、テストの自由度を保ちながらも、ある程度計画性を持たせること可能です。
テストセッションの終了後には、テスト担当者と関係者が集まり、テスト結果についての議論を行うのが一般的です。また、テストセッション中に使用されるテストセッションシートには、テストの実行手順、検出した不具合、得られた気づきなどが記録され、その内容が後の議論の材料となります。
このテストセッションシートの振り返りを通じて、さまざまな新しい洞察を得ることができるほか、以後のテストにおいてより効果的なアプローチを検討することが可能になります。セッションベースドテストは、探索的テストの柔軟性を活かしつつ、テスト結果を組織的に管理し、共有するための効率的な手段となります。
まとめ
探索的テストにはスピードやコスト面を中心に大きなメリットがありつつも、記述式テストのような網羅性は担保できないという弱点があります。それぞれに違った特徴があり、どちらが優れているというものではありません。
探索的テストだけでは品質の保証はできず、一方記述式テストだけではテストにおける気づきを十分に活かせない表面的なテストとなってしまう恐れもあります。
この2つのテストはそれぞれが補完的な関係にあることから、両方の特徴をしっかりと認識したうえで、適切に組み合わせてテストを実施することが大事です。
御社のプロジェクトにおいても、探索的テストを活用してみてはいかがでしょうか。
SHIFT ASIAについて
我々SHIFT ASIAは、ソフトウェア品質保証・第三者検証のリーディングカンパニーである株式会社SHIFT(プライム市場上場)の海外戦略拠点として、ベトナム・ホーチミンでマニュアルテストからテスト自動化やセキュリティテスト、インスペクションなどのソフトウェアの品質保証事業を手掛けながら、近年はオフショア開発にも事業領域を拡大させてきました。
経済産業省が発表したレポートによると、日本では2025年にはIT人材の不足が約43万人まで拡大すると言われるなど、特にIT業界ではエンジニア不足が大きな問題になっています。
SHIFT ASIAでは、こうしたIT人材の不足を解決する手段として、海外の優秀なエンジニア層を取り込み、彼らのリソースを活用しながら日本のお客様のニーズに応えるべく、優秀なベトナム人エンジニアの採用と育成に力を入れています。
SHIFT ASIAのサービスを支える人材の特徴
- 日本語コミュニケーション:日本語検定N1、N2以上を保有するテスター・エンジニアが100名以上在籍
- 英語コミュニケーション:英語対応のエンジニアが50名以上在籍
- 安心できる案件管理:在籍エンジニアのうち日本人が約10%を占め、日本人PMが案件管理をしっかり担当
- QA資格:国際的なテスト資格であるISTQBをはじめ、さまざま資格を保有するプロフェッショナルがテストおよび品質保証サービスを提供
なお、SHIFT ASIAに関する詳細資料は以下からダウンロードすることが可能です。
また、お困りごとやご相談などがございましたら、以下のお問い合わせからもお気軽にご連絡ください。
お問い合わせContact
ご不明点やご相談などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。